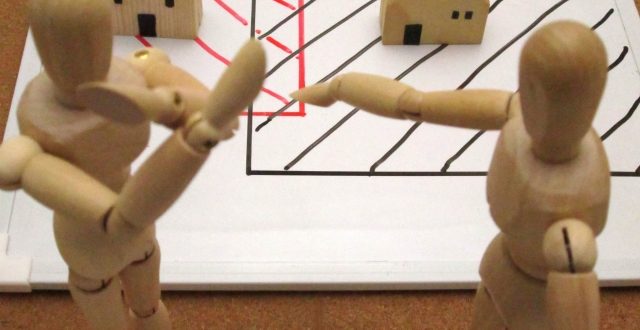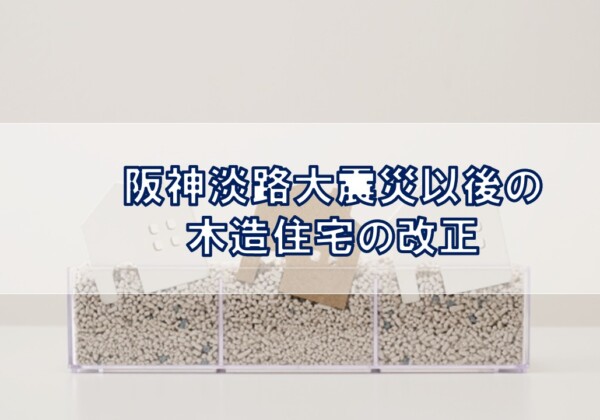毎日暑い日がつづいていおりますが古い住宅には断熱材が入っていないため夏は暑く冬はとてもさむく暖房をつけても温まり方は非常に悪いです。
(我が家の事です)
断熱材が日本で使われだしたのは今から40年ぐらい前の1970年ぐらいだそうです。
国が、一般住宅の断熱のガイドラインとして、昭和55年に省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能基準「省エネ基準」を定め、これが平成4年に「新省エネ基準」、平成11年に「次世代省エネ基準」、平成28年に「建築物省エネ法」と進化して、今に至ります。
ひと言で「断熱」といっても色々な種類・工法があります。工法は2種類、材料は3種類です。
工法
■充填断熱工法 (壁や天井、床などに断熱材を入れますが、柱と柱の間に断熱材を入れる工法)
充填断熱工法は、グラスウールやロックウールなどの繊維系断熱材を使います。
機械を使って吹き込む、またプラスチック系断熱材と合板などが一体となったパネルを貼り込むなどの方法で断熱材を充填します。
トータルコストが安いのが特徴ですが、すき間ができやすくなるのが欠点です。
■外張り断熱工法 (柱の外側に断熱材を張り付ける工法)
外張り断熱工法は、おもにプラスチック系の断熱材を、壁や屋根の外側から施工するもの。
メリットはすき間ができにくく、結露しにくいこと。コストは充填断熱工法に比べ高くなります。
材料
■無機質系
ガラスや鉱物などを細かい綿状にした断熱材で、「グラスウール」や「ロックウール」などがあります。
■木質系
古紙を再利用した「セルロースファイバー」のような木質繊維を利用した断熱材です。
壁や天井の中に吹き込む施工方法を用いることが一般的です。
■発泡プラスチック系
各種プラスチックを発泡させて製造する断熱材で、硬質ウレタンフォームはこの種類に属します。
種類によりボード状にして使う方法と、吹き付けて施工する方法があります。
断熱効果を高める方法
窓の断熱性を高める・・・複層ガラス(ペアガラス)・Low-E複層ガラス等を使用
断熱性に優れていて、冷暖房の消費を抑えることができるので、省エネ効果があります。
また、冷たい外気の影響を受けにくいために、冬場に発生する結露を発生しにくいそうです。
高断熱の家をつくるには、断熱材をしっかりと家の床・壁・天井に敷き詰めるだけでなく、窓ガラスの性能にも注目することが必要です。
現在の住宅で重視されている高気密な住宅を建てるためにも断熱性能の向上は欠かせません。
これから住宅購入を考えている方は参考にして下さい。
リニュアル仲介の渡辺でした。