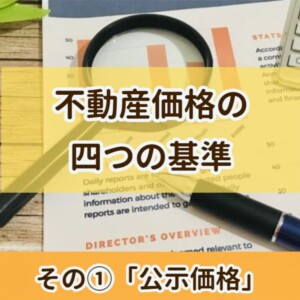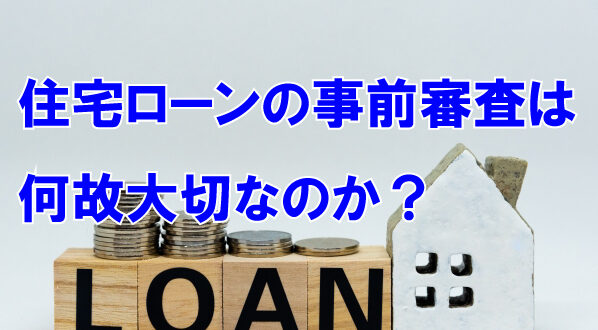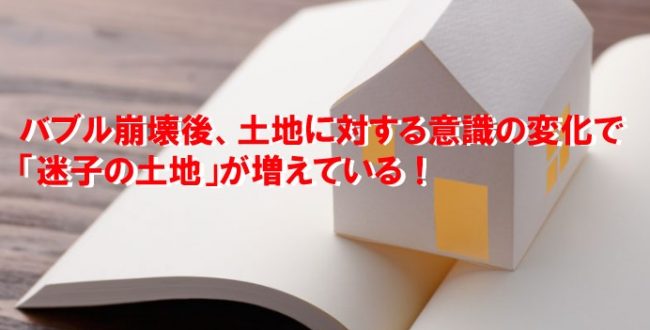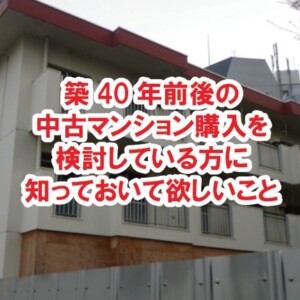阪神淡路大震災から丸30年が経過し、地震に対する意識も高まっています。大地震などの災害時、マンション室内に「籠城」して避難生活をするよう呼びかける動きが広がっているようです。戸建て住宅に比べて耐震性が高いことが多く、備蓄があれば避難所より快適に過ごせるといった意見もあるようです。そのような事態に備えるためにも、建物単位での備えを進めることが重要となります。
■災害時は自宅が「籠城」となる?!
東京都港区の20階建ての都営住宅「北青山三丁目アパート」は、災害時に「この建物は安全です。いまは室内にいてください」。このような館内放送を流す準備を進めているようです。重視していることは在宅避難の呼びかけとなります。いわば籠城作戦を決行して、住人の生命を守るためには籠城も一つの手となります。
「北青山三丁目アパート」に入居されている方の7割は高齢者世帯で幼い子どもを抱えたひとり親家庭も多いようです。世帯の大半が災害弱者で避難所までの移動もおぼつかない。いかに不安を抑えられるかが鍵となります。区の補助金を原資に電池で動くランタンの配布も始めるほか、保存が利く食品の試食品を配って各世帯に備蓄を呼びかける予定もあるそうです。各戸内部の様子を伝えてもらうため「無事です」と書かれたマグネットも配布されているようです。
■東京とどまるマンション普及促進事業という制度も存在する!
在宅避難対策をする物件は増えており、不動産購入時にはぜひ、確認をしてもらいたいと思います。災害に強い物件を「東京とどまるマンション」として公表する東京都では2024年10月末時点で500件超の登録があります。登録マンションを対象に補助金を設けたこともあり、2023年度からは年200件以上のペースで増えているそうです。人口の6割以上が集合住宅に住む東京都は「東京とどまるマンション」の登録物件を対象に2023年度に簡易トイレや炊き出し道具などの購入費支援を開始しています。2024年度には非常用電源の設置費用を補助する制度も始めたそうです。
マンションは耐震性能が高い物件が比較的多く、倒壊などによる犠牲者は出にくいとされます。建物に大きな損傷がなければ、自室にとどまるほうが避難所に身を寄せるより心身への負担が少なく、避難所での体調不良等を回避することにつながります。東京都などは電気や水道などが止まっても室内にとどまれるよう、1~2週間分の備蓄を推奨しています。しかし、マンションでは各戸単位の備えでは限界がある為、注意が必要です。
■災害時は自宅が「籠城」となるが、注意点もある!
ネックとなるのがトイレと高層階の孤立です。それはトイレの問題が挙げられ、備蓄で一番大事なのは簡易トイレとされているようです。マンションの場合、大きな地震によって建物内に張り巡らされた配管が損傷する恐れがあり、室内のトイレは使えないことが多いです。家族の人数分の簡易トイレを備えておけば、用を足すために避難所に移らなくて済みます。避難所のトイレは大変な状況になる事も多いことから、家族の対応分は確保したいところです。
高層階の孤立防止には、上層部に食料や飲料水などの備蓄倉庫を設けるのが有効となります。大地震が発生すると多くのエレベーターが自動停止し、復旧まで長い日数がかかると予想されます。1階から備蓄を高層階まで持って運ぶのは現実的ではないため、各住戸もしくは各階での備えが必要となります。
大阪市では上層階に備蓄倉庫を設けたり、下層階に上層階の住民が一定期間暮らせるスペースを確保したりする例が複数あります。非常用電源を設置したり、支援が必要な住民をあらかじめ把握するため任意の居住者名簿を作成したりするマンションもあるそうです。都市部の自治体も在宅避難の支援を強化しています。
人が集まって住むマンションには技術者や看護師など様々なノウハウを持つ住民がいる可能性が高く、人材面でのポテンシャルは高いそうです。特に分譲マンションは資産価値を高める観点からも管理組合で合意形成をして建物単位で災害への備えを進めるべきです。その為、不動産購入時にはこのような備えのあるマンションの有無を確認する事をお勧めします。
住民が押し寄せれば避難所はパンクします。在宅避難は地域にとって必要なことで、高い公益性がある事を把握しておいて欲しいです。マンションを自主避難所と位置づけ物資や情報を届ける仕組みを整備するなど行政の支援強化は急務となります。
なかなか不動産購入時に災害時の事まで気を回すことは難しいです。人間には「正常化の偏見」と言われるようですが、自分には災害は起こらないと考えてしまう、人間の心理が働いてしまうようですが、災害を経験した方は事前の備えの大切さを訴える方が多いことに想いを馳せ、災害時の対策もお忘れないようにしていただきたいと思います。
今後の参考にお役立て下さい。
法人営業部 犬木 裕